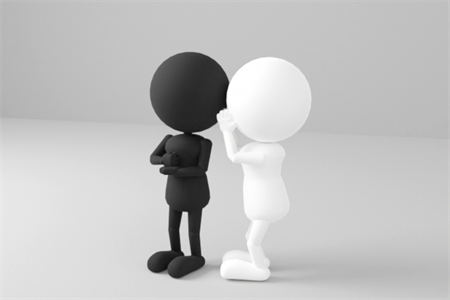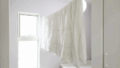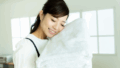仕事で
- 「少しお知らせしておきたい」
- 「念のため伝えておきたい」
と思う場面は意外と多いものです。そんなときに便利なのが「お耳に入れておきたい」という表現です。ただの報告や伝達よりも柔らかく、相手を立てながら情報を届けられるので、上司や取引先にも安心して使えます。
本記事では、
- このフレーズの正しい意味
- 敬語としての使い方
- シーン別の例文
- さらに言い換えや注意点
をわかりやすくまとめました。
初めて知る方も、すでに使ったことがある方も、読み終える頃には自信を持って活用できるようになりますよ。
「お耳に入れておきたい」の基本と敬語としての正しさ

本来の意味「お耳に入れる」とは?
「お耳に入れる」とは、相手に情報を伝える・知らせるという意味を持つ表現です。 単に「伝える」よりも、丁寧に配慮しながら相手に届けるニュアンスがあります。特にビジネスの場では、上司や取引先といった目上の人に対して使われることが多く、聞く側が受け取りやすい柔らかい響きを持っています。また、重要な内容だけでなく、補足的な情報を控えめに共有したい場面でも適しています。
敬語表現としての成り立ちとポイント
「耳に入れる」という動作に「お」をつけることで尊敬語の形となり、さらに語尾を丁寧に整えることでよりフォーマルな印象になります。 つまり「お耳に入れる」は相手を立てながら自分が情報を差し出す形となるため、信頼や安心を与えやすいのです。文章や会話でこの表現を用いると、こちらの姿勢が謙虚に見え、相手からも誠実な印象を持ってもらえます。そのため、特に目上への報告や注意事項を穏やかに伝える際に効果的です。
よくある誤用と注意点
- 親しい相手やカジュアルな場面で多用すると、過剰にかしこまった印象となり不自然です。
- 「お耳に入れておきますね」とだけ言うと、上から目線に聞こえてしまう場合があります。必ず前後に「念のため」「もし差し支えなければ」といったクッション言葉を添えると良いでしょう。
- さらに、緊急性の高い情報や必ず確認してほしい案件には「お耳に入れておきたい」ではなく「至急ご確認ください」など、より直接的な表現を使うほうが誤解が生じにくいです。
「お耳に入れておきたい」の語感とニュアンス

「伝える」「知らせる」との違い
「伝える」や「知らせる」よりも柔らかく、控えめに聞こえるのが特徴です。情報を押し付けるのではなく、相手の判断に委ねるニュアンスを含みます。また、「ご参考までに」といった控えめな姿勢と近く、聞き手に余裕を与える表現でもあります。
強制力を伴わないため、状況を知っておいてほしい時や前もって心づもりをお願いしたい時に最適です。さらに「伝える」は単純な動作、「知らせる」は結果重視なのに対し、「お耳に入れておきたい」はプロセスや配慮を重んじる表現だといえます。
控えめなニュアンスで角が立たない理由
「お耳に」という表現が、相手の立場を尊重しているため、角が立ちにくく、丁寧に受け取られやすいのです。このため、相手が忙しい状況や注意を促したい繊細な場面でも、必要以上に緊張感を与えずに情報を伝えられます。
また、ビジネスではしばしば「報告=責任追及」の印象が強くなりがちですが、「お耳に入れておきたい」とすることで、やわらかく事実だけを共有する姿勢を示せます。結果的に相手との信頼関係が損なわれにくく、スムーズなコミュニケーションの土台を築くことができます。
どんな場面で使うべき?タイミングと注意点

効果的に使える場面
上司への報告や相談
進行中の案件やちょっとした注意事項をさりげなく伝えたい時に有効です。相手に余裕を持って判断してもらえるため、急を要さない情報共有に向いています。
クライアントへの注意喚起
直接的に言うと強く聞こえてしまう内容も、「お耳に入れておきたいのですが」と前置きすることで柔らかく伝えることができます。信頼関係を維持しながら重要なポイントを知らせられるのが利点です。
会議前に必要な情報を共有する時
参加者に心の準備をしてもらいたい場合や、会議がスムーズに進行するよう事前に知らせたいことを控えめに伝える場面に適しています。プレッシャーをかけずに自然に受け入れてもらえます。
チームメンバーへの事前共有
全体連絡ほど大げさではないが、知っておいてもらうと役立つ情報を伝える場合に便利です。円滑なコミュニケーションを促す助けになります。
控えめにした方がよい場面
フランクな関係性の同僚との雑談
カジュアルな会話に差し込むと堅苦しさが際立ち、距離を感じさせることがあります。日常会話ではシンプルに「ちょっと知らせておきたいんだけど」と言う方が自然です。
プライベートな場面
家族や友人とのやり取りでは過剰にフォーマルな印象を与え、距離感を生むこともあります。親しい関係ではむしろ簡潔な言葉の方が伝わりやすいです。
緊急性のある連絡
急を要する内容では、遠回しな「お耳に入れておきたい」よりも「至急ご確認ください」といった直接的な表現の方が適切です。
適切に使うための判断基準
「これは相手に知っておいてほしいが、強調しすぎたくない」という場面で使うと自然です。相手との関係性や状況に応じて、柔らかく前置きしながら伝えることで、過度なプレッシャーを与えずに必要な情報を届けられます。つまり、伝えたいことの重要度が「中程度」である時に使うのが最も効果的です。
世代・業界による受け止め方の違い

年配の方には丁寧な印象を与えるケース
フォーマルさを重んじる方には好印象を持たれやすいです。特に長く社会経験を積んだ世代では、伝統的な言葉遣いに親しみを感じるため「お耳に入れておきたい」といった表現は礼儀正しいと評価されます。重要事項を控えめに共有する姿勢が、信頼につながることも多いです。
若い世代には堅苦しく感じられる場合
若い層には少し堅苦しいと感じられる可能性があります。普段の会話で聞き慣れない表現のため、かしこまりすぎていると受け取られる場合があります。そのため、相手が20〜30代中心の職場では「念のためお伝えします」や「軽く共有します」といった言い換えを選んだ方が自然に伝わります。相手に合わせた調整が必要です。
業界ごとの受け止められ方
金融・官公庁
フォーマルさがプラスに働きやすく、相手に安心感を与えます。厳格な業界文化に合致するため、積極的に使える場面が多いです。
IT・ベンチャー
スピード感やフラットな文化を重視する環境では、少し古風な印象になることがあります。ただし役員や外部パートナーへの報告時には逆に信頼性を強調できます。
サービス業
お客様対応としては高評価で、丁寧で柔らかい言葉が好まれる傾向にあります。接客やクレーム対応で「念のためお耳に入れておきたいのですが」と用いると、配慮ある姿勢として好印象を残しやすいです。
ビジネスシーン別の使用例文

上司への報告メール
「一点、先日の件についてお耳に入れておきたいことがございます。状況は大きな問題ではございませんが、今後の判断材料としてご承知いただければ幸いです。」
このように前置きを加えることで、ただ知らせるだけでなく配慮ある姿勢を伝えることができます。文章にクッション言葉を添えると柔らかく受け取られやすいです。
クライアントとの会話
「念のためお耳に入れておきたいのですが、来週のスケジュールに変更がございます。大きな影響はございませんが、ご確認いただければ幸いです。」
クライアントには安心感を与えるため、変更点と影響範囲を併せて説明するとより丁寧です。必要に応じて代替案や補足も添えると信頼感が増します。
チーム内での共有
「みなさんにお耳に入れておきたい情報として、新しいルールを共有します。すぐに対応が必要ではありませんが、次回のプロジェクトから適用されますので、早めに把握しておいてください。」
このように伝えると、メンバーは余裕を持って準備できます。状況に応じて背景や目的を簡潔に補足すると理解が深まります。
トラブル報告
「少々トラブルがありまして、お耳に入れておきたいと存じます。現時点では大きな影響はございませんが、念のためにお知らせいたします。具体的には、納期に関する一部遅延が予想される状況で、原因を特定し改善策を検討中です。今後の流れに影響が出る可能性もありますので、早めにお耳に入れておきたいと考えました。」
このように詳細を補足し、影響範囲や対応方針を簡潔に伝えると、相手に安心感を与えやすくなります。問題を隠さず、適切に共有する姿勢は信頼構築にもつながります。
提案やアドバイス
「新しい企画について、お耳に入れておきたい点がございます。具体的には、現状の計画に加えてSNSを活用した広報戦略を組み込む案です。今すぐ決定事項ではありませんが、参考としてご検討いただければ幸いです。」
このように伝えると、相手にプレッシャーを与えずに意見や提案を共有できます。
- 「あくまで参考までに」
- 「ご意見をいただければ」
と添えると、より柔らかい印象になります。」
NG例:逆効果になってしまう使い方
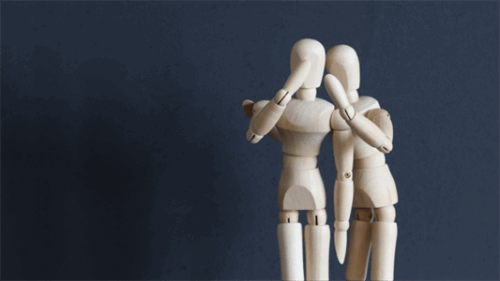
自分本位に聞こえるケース
「お耳に入れておきますから!」など強調しすぎると押し付けがましく聞こえます。特に、相手が聞く体制を整えていない場面で唐突に用いると、「自分の意見を無理に通そうとしている」と誤解されかねません。言葉だけでなく、声のトーンや文脈にも注意が必要です。
報告が遅れて「言い訳」に見えるケース
「実は前から知っていたのですが…」という流れで使うと不信感を与えることがあります。特にビジネスでは「なぜもっと早く伝えてくれなかったのか」と受け取られ、信頼を損なう可能性があります。事実をやわらかく伝えるための表現であっても、情報が遅れると逆効果になりやすいのです。早めに共有することが何より大切です。
相手にプレッシャーを与えてしまうケース
「お耳に入れておきたいので、確認お願いします」と過度にセットで使うと命令的に感じられます。本来は控えめなニュアンスのある表現ですが、依頼文と強く組み合わせると「強制的な確認依頼」のような響きになります。その結果、相手に不要な負担感を与える場合もあります。
必要なら、
- 「ご参考までに」
- 「もしご都合がよろしければ」
といった柔らかいクッションを添えると印象が和らぎます。
言い換え表現でニュアンスを調整する
- 「念のためお伝えします」
- 「ご報告させていただきます」
- 「事前にお知らせしておきます」
- 「ご承知おきください」
- 「お知らせまでに」
- 「一応共有させていただきます」
- 「補足としてお伝えします」
- 「参考までにご案内いたします」
これらの言い換えを状況に応じて使い分けると、相手に与える印象を柔らかくしたり、必要に応じて少しフォーマルさを強めたりできます。
たとえば、上司やクライアントには「ご報告させていただきます」「ご承知おきください」を用いると真面目さが伝わります。
一方で、同僚や社内向けには「一応共有させていただきます」「参考までにご案内いたします」といった表現の方が親しみやすく、重たすぎない雰囲気を作れます。
補足で「大きな問題ではないのですが」「緊急性はありませんが」といった前置きを添えるとさらに柔らかく伝えられます。また、「今後の判断材料として」や「ご安心いただけるように」と目的を補うと、より誠実で分かりやすい伝え方になります。
「お耳に入れておきたい」と一緒に覚えたい類義表現

「念のために」系
- 「念のためお知らせします」
- 「万一に備えて共有します」
など、相手に負担をかけずに控えめに情報を伝えたいときに便利な表現です。 リスクを避けたい場面や、補足情報を伝えるときによく使われます。例えば「念のためお知らせしますが、本日の会議は予定通り開催されます」といった形で使うと自然です。
「軽くお知らせ」系
- 「ちょっとお伝えしておきます」
- 「参考までに」
など、重要度が高くない情報や雑談に近い形で伝える時に用いられます。相手に深刻に受け止めてほしくない場合や、気軽に共有したい情報を渡す場面に最適です。「参考までに、本日から新しいツールの試験導入が始まっています」と添えると良いでしょう。
「重要な報告」系
- 「必ずご確認いただきたいのですが」
- 「至急お伝えします」
など、相手に行動や確認を求めたい時に使われます。
強めのニュアンスを含むため、重要度が高い内容に絞って使用すると効果的です。例えば「至急お伝えします。本日のシステム障害についての詳細を確認いただきたいです」と伝えると、相手の注意をしっかり引くことができます。
メールと口頭での使い分け

メールでは丁寧に伝えるポイント
前置きで「突然のご連絡失礼いたします」などを添えると自然です。 さらに、件名や冒頭で「念のためお耳に入れておきたい件がございます」と記すと読み手が心構えを持ちやすくなります。メールは文字だけで伝えるため、相手が誤解しないように背景や補足説明を多めに入れると安心です。また、最後に「以上、ご参考までに」と締めると程よい丁寧さが加わります。
口頭ではやわらかく伝える工夫
声のトーンを柔らかくし、「よろしければ…」を添えると好印象です。特に会議や雑談の中で取り上げる場合は、前置きとして「少しだけお耳に入れておきたいのですが」と切り出すと自然です。視線や表情を和らげることで、言葉以上に柔らかさを伝えることができます。短時間でのやり取りが多い口頭コミュニケーションでは、要点をまとめつつ安心感を与える姿勢が大切です。
前後の文脈で自然に組み込む方法
「念のためお耳に入れておきたいのですが…」と切り出すとスムーズです。その後に「今すぐ対応は不要ですが」「次回のために知っていただければ」と添えると相手は安心して聞き入れられます。特に忙しい相手に伝える場合は、要点を最初に述べてから補足を加えると理解されやすいです。文脈全体の流れを整えることで、堅苦しくなりすぎず自然に受け止めてもらえます。
関連フレーズとの組み合わせで印象アップ

「ご確認ください」と組み合わせる
「念のためお耳に入れておきたいことがありますので、ご確認ください。」
このように伝えると、相手に確認をお願いする際も強制感が薄れ、あくまで「ご参考までに」といった印象になります。特に、相手に考慮してほしい資料や補足情報を示す時に有効です。
「よろしくお願いします」と組み合わせる
「お耳に入れておきたい内容がございます。どうぞよろしくお願いいたします。」
依頼の一文と組み合わせると、単なる報告に温かさが加わり、相手に協力をお願いしやすくなります。業務上の依頼や確認事項の前に添えると、よりスムーズなやり取りが可能です。
他のビジネス定型文と合わせるコツ
「今後の参考までに」「お手数ですが」などと合わせると柔らかさが増します。たとえば「今後の参考までにお耳に入れておきたいのですが…」とすると、単なる情報提供から相手の学びや気づきを促すニュアンスが生まれます。
また、「お手数ですがご確認ください」と併せて使えば、謙虚さと丁寧さを同時に表現できます。相手に配慮を示しつつ、必要なアクションを自然に促す効果が期待できます。
英語でどう表現する?

Just to let you know
カジュアルかつ丁寧に「お知らせまでに」と伝えるニュアンス。社内メールや口頭での軽い伝達に向いており、相手に強制感を与えず気軽に共有できます。
例えば
「Just to let you know, the meeting will start a bit later today.」
といった使い方が一般的です。
For your information (FYI)
フォーマルにもカジュアルにも使える便利な表現。
ビジネスメールでは
「FYI: Please find attached the updated report.」
といった形で資料を共有する時によく使われます。
社内だけでなく顧客や取引先とのやり取りにも応用可能で、無駄なく情報を届けたいときに適しています。
カジュアル表現との違い
「By the way(ちなみに)」はより雑談寄りの印象になります。例えば「By the way, did you see the new design?」のように話題を切り替える時に使われます。
これに対し「Just to let you know」や「FYI」は、情報をきちんと伝える目的を持つ点で異なります。目的や場面に合わせて選ぶことで、英語表現でも日本語同様に相手への配慮を示すことができます。
簡単チェックリスト|今日から使えるポイント3つ

敬語として正しく使えているか
尊敬語・謙譲語のバランスを確認し、相手に対して失礼になっていないかをチェックしましょう。特に「ご報告させていただきます」「ご承知おきください」などと置き換える際には注意が必要です。
文脈や相手との関係性に合っているか
親しい同僚には堅苦しすぎないか、逆に上司やクライアントには軽くなりすぎていないかを判断するのがポイントです。場面や業界の文化に合わせて使い分けると効果的です。
一言添えて印象を良くできているか
「大きな問題ではありませんが」「ご安心いただけるように」など補足のクッションを入れると、より柔らかい印象を与えられます。相手に安心感を持ってもらうことが大切です。
伝える内容の重要度を見極めているか
緊急案件や必ず確認が必要なケースでは「お耳に入れておきたい」では弱いため、別の直接的な表現に切り替える必要があります。
使う頻度が多すぎないか
繰り返し使うと堅苦しく感じられるため、同じ文章や会話で何度も登場しないように工夫しましょう。
まとめ
「お耳に入れておきたい」は、相手に配慮しながら情報を伝えるための便利な敬語表現です。ただし、使いすぎると堅苦しく聞こえることもあるため、文脈や相手に合わせて調整することが大切です。たとえば上司やクライアントにはフォーマルに、同僚や社内の気軽なやり取りでは少し柔らかい言い回しに切り替えると自然です。
また、状況に応じて「念のため」「ご参考までに」といったクッション表現を添えると、安心感や誠実さをプラスできます。特にビジネスでは、単に伝えるだけでなく相手が受け取りやすい形に整えることが信頼につながります。
場面に応じた言い換えや組み合わせを意識することで、より印象の良いコミュニケーションが実現できます。さらに、英語表現や関連フレーズもあわせて身につけておくと、国際的な場面や多様な相手とのやり取りにも応用でき、表現の幅が大きく広がります。